公開日: |更新日:
腎臓の機能を人工的に代替する医療行為である人工透析ですが、一般社団法人 全国腎臓病協議会(全腎協)によると1か月に40万円程度の医療費がかかると言われています。この治療費が大きな負担となる方は多いと思いますが、東京都では人工透析患者に対して助成する制度が存在します。
人工透析には「血液透析」と「腹膜透析」の2通りがありますが、このうち「血液透析」は一般的に週3回程度の通院・治療を必要とします。1回あたりの治療費が3万円程度となっており、単純計算すると週3回×3万円×4週間で1か月あたり36万円もの支払が必要になってきます。
また、「腹膜透析」に関しては月に1回程度の通院で管理しながら自宅で行える透析治療となっていますが、透析液やカテーテルなどにかかる費用として1か月あたり30万円から50万円程度かかると言われています。
参照:全腎協(https://www.zjk.or.jp/kidney-disease/expense/dialysis/)
お金がかかるというイメージの強い人工透析治療ですが、国や東京都からの助成制度を上手く活用することにより負担を減らすことができます。自己負担限度額や現物給付などの助成制度について紹介します。
認定を受けた疾病に関する医療を指定された医療機関で受けた場合、医療保険等適用後の自己負担分が助成されるというものになります。東京都でも以前より実施されていましたが制度が改正されました。従来は医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日以降は、「指定医が重症度分類を満たしていると診断した日」まで遡って医療費助成を開始できることとなりました。医療費等の3割を自己負担している場合には負担割合が2割となり、また自己負担上限額を超えた自己負担額は全額助成となります。
「小児慢性特定疾病」にかかっている児童などについては、健全育成の観点から患児家庭における医療費負担の軽減を目的として自己負担の一部を助成してもらうことができるようになっています。対象疾病群は16種類あるのですが、その中の1つに「慢性腎疾患」が含まれています。これは18歳未満の児童が対象となっており、実施主体は「都道府県」「指定都市」「中核市及び児童相談所設置市」となっています。
重度心身障害者医療費助成制度は、東京都内に住所を有する方で要件を満たす場合に医療費の助成を行う制度となっています。その要件の中の1つに「身体障害者手帳1級・2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)」というものがあり、これに該当する人工透析患者は制度を利用することができます。ただし、所得制限基準額を超える方や生活保護受給者など、一部対象除外となる方がいらっしゃいますので注意が必要です。
「マル都医療券」は東京都が実施している医療費助成制度です。この「マル都医療券」が交付される制度はいくつかあるのですが、その中に「人工透析にかかる医療費助成」というものがあり、「特定疾病療養受領証」の交付を受けている方が対象となります。内容としては各医療保険などを適用した人工透析において、自己負担額のうち月額1万円を上限として助成が受けられるものとなっています。
健康保険に加入しており、なおかつ人工透析を必要とする患者さんが受け取れるものになります。保険証とともに医療機関の窓口に提出すると、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額10,000円とすることができます。
前述しました通り、人工透析を必要とする患者さんを対象に、自己負担額を1つの医療機関あたる月額10,000円とすることができるのが特定疾病療養受療証になります。これは健康保険の高額療養費制度の一環として実施されているもの。健康保険の高額療養費制度は、医療機関や薬局に支払った金額のうち上限金額を超えた分が支給されるというものですが、年齢や所得額によって上限が変ってきます。その上で、人工透析は特例として特定疾病療養受療証が受け取れるようになっているというのが注目すべきポイントになります。
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf)
特定疾病療養受療証の交付を受けるためには、基本的にはお住まいの自治体窓口に必要書類を提出することが必要になります。しかしながら、各自治体によって、提出する書類や手順などが微妙に異なる場合もあります。ここでは一例として、千代田のケースをご紹介しますので、ご参考までに。実際に申請する際は、お住まいの自治体の申請方法をご確認ください。
出典:千代田区公式HP(https://www.city.chiyoda.lg.jp/lifeevent/hoken/tokuteshippe.html)
千代田区の場合は、公式HPからダウンロードできる「国民健康保険特定疾病認定申請書」ならびに医師による診断書または意見書となっています。
上記の必要書類を区役所2階の国民健康保険係の窓口に持参、または国民健康保険係宛に郵送。直接窓口に持参すれば、即日発行が可能としています。
以上ここまで人工透析を長く続けていくにあたってお得に快適にできるような方法を紹介してきました。
これらの各種助成制度を利用していただいて、高額な費用が掛かることがある人工透析の価格を抑えて費用に心配することなく治療に専念することができます。
国や東京都が提供する医療サービスを活用し快適な人工透析ライフを送っていきましょう。
腎臓の働きが弱まっても、仕事や家庭との両立を諦める必要はありません。
東京には、夜間や休日、さらには睡眠時間を活用できるオーバーナイト透析まで、ライフスタイルに合わせた多様な治療を提供するクリニックがあります。
通いやすい立地や快適な治療環境により、長時間の透析もリラックスして過ごせるよう工夫されています。
「命を守る治療」であると同時に「自分らしい生活を続けるためのサポート」として、あなたに合った透析クリニックを見つけてみてください。
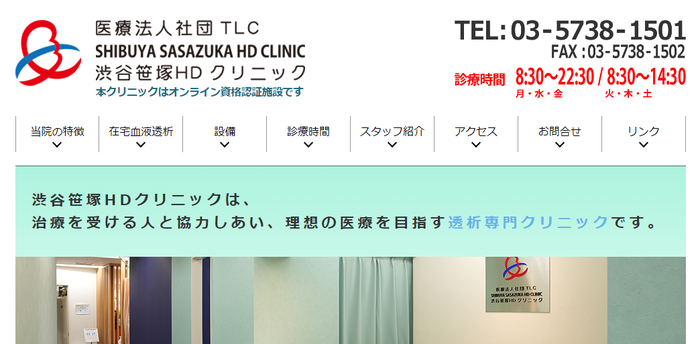
引用元:https://sasazuka-clinic.jp/
新宿、渋谷からもアクセスしやすい笹塚駅徒歩1分。仕事帰りや出勤前でも立ち寄れる便利な立地。
月・水・金は朝8時半から夜23時まで透析が可能。残業後や早朝でも治療を続けられます。在宅透析も相談可能。
全てのベッドでオンラインHDF透析を受けられるので、混雑や時間帯を気にせず治療できます。
お問合せ:0120-051-137

引用元:https://tulip.clinic/dialysis/
平日だけでなく土日も透析に対応しているため、予定に左右されず治療を継続できます。平日に休むことが難しい場合や送り迎えが必要な方も、家族の休みに合わせて無理なく通院できます。
腹膜透析と血液透析を導入時から併用でき、患者の腎機能や生活スタイルに合わせた柔軟な治療を選択可能です。
初めての透析もすべて外来で導入できるため、入院の負担なくすぐに治療を始められます。
お問合せ:03-6805-1836

引用元:https://www.tokyonext.jp/
金曜23時から翌朝7時までのオーバーナイト透析で、眠っている間に8時間の治療が完了。日中の自由な時間を確保できます。
43床のベッドを備え、有料シャワールームも完備。混雑時でもゆとりをもって快適に透析が受けられます。
他院で追加料金がかかることもあるオーバーナイト透析が、通常と同じ費用で受けられます。
お問合せ:03-5615-1566
ライフスタイルに合わせて選ぶ
東京都内&近郊の
人工透析クリニック